本多正信の【死因】や【最後の様子】について、短くまとめると、以下のとおりです。
- 本多正信の死因は、老衰または病死
- 正信は、1616年7月20日に亡くなった
- 正信が死ぬ前に、息子・本田正純に家督をゆずって引退した
- 正信は、【3万石以上の褒美をもらってはいけない】という言葉を息子・本田正純に残した
- 正信には、木村敦明さんという子孫がいる
- 正信の死後、【宇都宮釣り天井事件】という歴史的事件が起こった
この記事では、本多正信の最期の様子について、ひと目で分かるようにまとめました。
本多正信の最期と死因について知りたい方にとって、この記事は必ずお役に立つはずです。
これを読んで、本多正信の最期についての疑問を、スッキリと解消していただければ幸いです。
専門サイト【最期と死因ドットコム】へようこそ。
どうぞ、ごゆっくりお過ごしくださいませ。
本多正信の【死因】と【最後の様子】
本多正信の【死因】
【結論】本多正信の死因は、老衰または病死
本多正信の死因は、はっきりとはわかっていませんが、老衰または病死であると考えられます。
正信は、79歳という、当時としてはかなりの高齢で亡くなっています。
そのため、老衰であると考えられます。
しかし、筆者の個人的な見解でしかありませんが、正信の死因は糖尿病に関係する病死ではないかと思っております。
実は正信は、亡くなる3年前の1613年に、徳川家康から万病円と八味円という薬を与えられているのです。
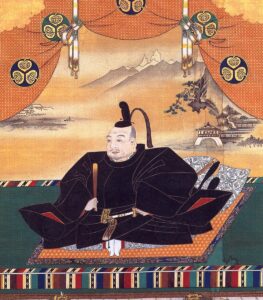
徳川家康
引用元ウィキペディアより
万病円は、その名の通り万病に効くとされていた万能薬。(実際の効果としては、便秘と腰痛に効くといわれているらしい。)
八味円は、現在でも八味丸という名前で服用されている糖尿病の薬のこと。(動脈硬化や神経衰弱に効果があるともいう)
薬マニアだったという家康は、おそらく正信が糖尿病などで苦しんでいることに気がついていたため、この万病円と八味円という薬を与えたのでしょう。
本多正信が【亡くなった日】と【享年】
【結論】西暦1616年7月20日(元和2年6月7日)、享年79歳
実は正信が亡くなる2ヶ月ほど前の【1616年6月1日】に、主君である徳川家康が亡くなっているのです。
正信は家康から友と呼ばれたといいますが、家康のあとを追うように亡くなったのでした。
本多正信の子孫の現在
【結論】本多正信の子孫には、現代に木村敦明さんという人物がいる
本多正信には、いくつもの系統で子孫が現代も生き残っておられますが、その中でも直系と言えるのは木村敦明さんではないでしょうか。
苗字が本多から変わっているものの、木村さんは令和元年に、本多正純が藩主を務めた栃木県小山市で公演をなさっておられました。
また、本多正信の次男である本多政重の系統も続いており、昭和に貴族院議員・本多政樹さんという方が活躍なさっておられました。
その本多政樹さんの子孫もまた、現在続いていると考えられます。
【本多正信の生涯と最期】をザッと解説
本多正信の生涯を、ハイライトでザッと解説いたします。
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1538年 | 三河国で生まれる |
| 1560年 | 桶狭間の戦いで膝を負傷 |
| 1563年 | 三河一向一揆が起こり、家康に敵対 |
| 1570年~1582年 | 徳川氏に帰参 |
| 1582年 | 本能寺の変が起こり、伊賀越えに従う |
| 1586年 | 従五位下、佐渡守に叙位・任官される |
| 1590年 | 相模国玉縄で1万石の所領を与えられ、大名となる |
| 1600年 | 関ヶ原の戦いで徳川秀忠の軍勢に従い、真田昌幸・幸村に大敗 |
| 1601年 | 朝廷との交渉に尽力し、徳川家康が将軍職に就任する手助けをする |
| 1603年 | 江戸幕府が開設され、家康の側近として幕政を主導する |
| 1605年 | 徳川秀忠が第2代将軍になり、正信は江戸で幕政に参画する |
| 1607年 | 秀忠付の年寄(老中)になる |
| 1612年 | 子の正純の家臣・岡本大八による朱印状偽造が発覚する(岡本大八事件) |
| 1613年 | 大久保長安事件、大久保忠隣失脚に関わったとされるが、同時代の史料は確認できない。また、家康から万病円200粒と八味円100粒を与えられる(『駿府記』) |
| 1616年 |
4月に家康が死去し、家督を嫡男の正純に譲り隠居して一切の政務から離れ、6月7日に死去。享年79。 |
誕生から三河一向一揆での追放まで
本多正信は、三河国の豪族の子として誕生し、のちに主君・徳川家康を裏切って追放処分とされています
正信は、武将・本多俊正の次男として三河国で誕生し、徳川家康に部下として仕えています。
その後、正信は1560年の桶狭間の戦いに参戦し、足を負傷して歩行が困難になったといいます。
1563年の三河一向一揆をご存知でしょうか?
家康の生涯で、三方ヶ原の戦いや伊賀越えと並んで、三大危機と呼ばれた苦難の一つなのですが、正信はその三河一向一揆で家康を裏切り、三河国から逃亡・出奔しているのです。
本能寺の変から伊賀越え
1563年に出奔つまり家出をした本多正信は、1582年には家康のところへ戻ってきています。
1563年の三河一向一揆で家出した正信ですが、のちに家康のもとへ戻ってきているわけですが、戻ってきた時期については諸説あります。
1570年の姉川の戦いの頃から、1582年の本能寺の変の頃まで、このあいだに戻ってきたとされています
神君伊賀越えは、三河一向一揆や三方ヶ原の戦いとならぶ、家康の三大危機の一つです
本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれた直後に、つまり明智光秀の追手に家康が追われた際の、京都から三河(愛知県東部)へ逃亡する途中で、正信は家康の部下として戻ってきたといわれているのです
このとき、本多正信のなかで、家康に対する気持ちが変わったのだと思います。
正信が裏切った徳川家康は、もう一度自分を信じて、家臣として受け入れてくれたのです。
それ以来、本多正信は徳川家康から【友】と呼ばれるほどの活躍をみせるようになります。
主君・徳川家康を守り、天下を取らせるために。
ところが、そんな頭脳派・本多正信の前に、難敵が立ちふさがるのです。
表裏比興の者・真田昌幸です。
(表裏比興の者とは、表と裏の顔を使い分ける食わせ者・兵法の達人という意味です)

真田昌幸
引用元ウィキペディアより
関ヶ原の戦い
正信は、関ヶ原の戦いにおいて、真田昌幸に大敗するという大失態を犯しています。
【1600年】の関ヶ原の戦いと、【1615年】の大坂の陣において、本多正信を2度にわたって苦しめたのが真田昌幸とその子である真田信繁(幸村)の真田親子です。
1600年、関ヶ原の戦いが起こったとき、本多正信は徳川家康とは別行動をとっていました。
正信は、家康からの命令で、家康の息子・徳川秀忠を補佐していました。

徳川秀忠
引用元ウィキペディアより
秀忠は、徳川軍団の主力38000人を率いて、信濃国(長野県)の上田城を通って、美濃国(岐阜県南部)へ向かっていました。
正信は、徳川四天王のひとり榊原康政とともに、徳川秀忠のそばにいました。
上田城を守っていたのは、真田昌幸そして真田信繁の2人。
秀忠は、正信が止めるのも聞かずに、真田昌幸が守る上田城の攻撃を指示してしまいます。
ちなみにこのとき、武闘派の大久保忠隣も、上田城を攻撃することを主張したといいます。
実は真田昌幸は一度、徳川軍団を撃破した経験がありました。
秀忠はそれを恨みに持っていたのかもしれません。
結果は秀忠の惨敗。
秀忠は真田昌幸に手玉に取られ、天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いに間に合いませんでした。
家康は、秀忠と徳川本隊がいなくても、関ヶ原の戦いに勝利。天下はほぼ徳川家のものとなりました。
正信は、真田昌幸に手玉に取られたために、秀忠を遅刻させるという、大失態を犯したのでした。
その後、真田昌幸と息子の信繁(幸村)は、紀州(和歌山県)の九度山に幽閉され、昌幸は1611年に死去。
真田昌幸の長男・信之は、父の葬儀について本多正信に相談したところ
「お前の父は重罪人である。
そのため、幕府の意見を確かめてから、葬儀を行うようにせよ」
といわれています。
正信は、おそらく昌幸を恨んでいたのでしょう。
大坂の陣
本多正信は、1615年の大坂の陣に参戦した翌年の1616年に亡くなっています。
1615年、大坂夏の陣で、真田昌幸の息子・信繁(幸村)によって、徳川家康は追いつめられています。
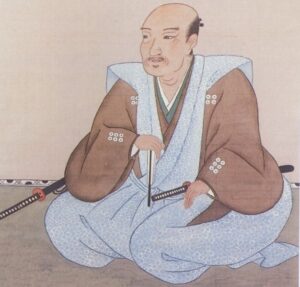
真田信繁/真田幸村肖像:上田市立博物館所蔵品:Wikipediaよりパブリックドメイン
このとき、正信は軽装で秀忠のそばにつきそっていたといいます。
徳川軍団は、大坂城に立てこもっていた豊臣秀頼と淀殿を攻撃。
豊臣軍団には、かつて正信を苦しめた真田昌幸の子・真田信繁(幸村)がいました。
真田信繁は、最期の最期で凄まじい猛攻により、家康をおいつめます。
家康は、2度も切腹をしようとしたほどです。
正信はこのとき、おそらく背筋が凍りつくような思いをしたことでしょう。
なんといっても、自分の恩人であり、生涯を捧げる覚悟をした主君・家康が、危機に瀕していたのですから。
ところが正信は、家康からの絶大な信頼を勝ち取っていたため、息子の秀忠を託されていました。そばを離れるわけにはいかなかったことでしょう。
真田信繁の猛攻も長くは続かず、結局真田信繁は戦死。
豊臣秀頼も淀殿も、ともに自害して果て、天下は徳川のものとなったのです。
最期
翌年の1616年、徳川家康が死去。
そのあとを追うようにして、正信もまた、この世を去ったのです。まるで生きる意味を失ったかのように。
余談ですが、真田昌幸の長男である真田信之は、正信の親戚である本多忠勝の娘・稲姫を妻としていました。
その縁で、本多忠勝は昌幸や信繁の命乞いをしたといいます。

本多忠勝
引用元Wikipediaより
「昌幸・信繁の命を救ってくれないのならば、私は娘婿の真田信之とともに城に立てこもり、殿(家康)を相手に戦をいたします」
この忠勝の強情な態度に折れた家康は、処刑するはずだった真田昌幸らを、九度山幽閉で許したのでした。
忠勝は正信のことをとても嫌っていたといいますので、もしかすると正信を困らせるために、昌幸らの命を救ったのかもしれません。
本多正信の【辞世の句】または【残した言葉】とその意味を解説
【結論】本多正信が残した言葉には、息子・正純に対して残した
「3万石以上の褒美をもらってはいけない」
というものがある
正信はいつも、息子の本多正純に対して、【3万石以上の領地を褒美としてもらってはいけない】と言っていたといいます。
本多正信は、徳川家臣団で嫌われていました。
遠縁の本多忠勝も、関ヶ原の戦いでともに徳川秀忠を補佐した榊原康政も、正信のことを嫌ってめちゃくちゃに悪口を言いまくっていたのです。
正信の長男・本多正純は、父親に似て優秀で賢く、家康から特に気に入られた人物でした。
「お前は私が亡くなったら、必ず大きな領地をもらうことになるだろう。
3万石まではありがたくもらうと良いが、それ以上もらったら災いが降りかかる」
そのような不吉な予言を残し、正信は亡くなりました。
その後、本多正純は徳川秀忠の信頼を勝ち取って、権力をほしいままにしていました。
そして父の予言通り、宇都宮城15万5千石の領地を秀忠から与えられたのち、【宇都宮釣り天井事件】によって失脚することになるのです。
しかもその事件は、本多正信がすべてをかけて仕えた主君・徳川家康と、正信をいつも助けてくれた恩人・大久保忠世の子供達が原因でした。
本多正信の【死後に起こった歴史的な出来事】とは?
【結論】本多正信の死後、【宇都宮釣り天井事件】という事件が起こった。
本多正信の死後、1622年に、【宇都宮釣り天井事件】という、将軍・徳川秀忠暗殺未遂事件が勃発し、正信の息子・正純は領地を没収されて没落します。
実は、正信がまだ生きていた頃、一つの事件が起こりました。
1614年、大久保忠隣という武将が、正信・正純親子との権力闘争に敗北して罠にひっかかり、領地を没収されていたのです。
この大久保忠隣という武将は、正信が家康のもとに戻ってくる際に、正信を何かと助けてくれた大久保忠世という武将の息子でした。
大久保忠隣は、とても真面目で、徳川家の武将たちから頼りにされていた人望の厚い人物だったのです。
徳川家臣団は、大久保忠隣を失脚させた本多正信・正純親子をとても恨みました。
そして本多正信の死後、正純は自分の権力におごりたかぶり、加納御前という人物を怒らせています。(加納御前は、徳川家康と築山殿の長女で、亀姫という名前で有名)
加納御前とその孫・奥平忠昌は、幕府からの命令により、宇都宮という豊かな土地を取り上げられ、一段格の低い下総古河という地に引っ越しをさせられたのです。
しかもその取り上げられた宇都宮城の城主となったのが、本多正純だったのです。石高は15万5千石。父・正信が忠告した3万石を大きく超える石高でした。
これに加納御前は激怒します。彼女は、宇都宮城を本多正純に奪われたと感じたのです。
しかも正純親子が失脚に追い込んだ大久保忠隣は、加納御前の娘の嫁ぎ先で、加納御前にとっては頼りになる親戚だったのです。
そのため、加納御前は本多正純に恨みを抱き、宇都宮に釣り天井が仕掛けられている、という陰謀をでっちあげたといわれています。
日光東照宮で父・家康の七回忌の帰りに宇都宮城に宿泊する予定だった弟・徳川秀忠は、姉・加納御前からの通報を聞いたのでした。
これを知った徳川秀忠は、自分を釣り天井という仕掛けで暗殺しようとした本多正純に激怒。
正純は領地を没収され、1637年に73歳で寂しく亡くなったといいます。
本多正純は、父親の本多正信から注意された【3万石】を大きく超える15万5千石をもらってしまい、周囲からの妬みをうけたのでしょう。
また、この宇都宮釣天井事件の黒幕は、大久保忠隣を失脚させられたことに怒っていた徳川家の重臣・土井利勝だったともいわれています。
- 正信がすべてを捧げた主君・徳川家康の娘・加納御前
- 正信をいつも助けてくれた恩人・大久保忠世の子・忠隣
この二人が、本多正純失脚の原因と考えられるのです。
まとめ
この記事をまとめますと、以下の通り
この記事を短く言うと
1,本多正信の『死因』は?
死因は、老衰または病死
2,本多正信が【亡くなった日時】は?
西暦1616年7月20日(元和2年6月7日)
享年79歳
3,本多正信の【最後の様子】とは?
最後の様子は、息子の正純に家督をゆずって引退した
4,本多正信の【最期の言葉】とは?
最後の言葉は、息子の正純に対して、【3万石以上の褒美をもらってはならない】というもの
5,本多正信の【子孫】とは?
子孫には木村敦明さんや、貴族院議員の本多政樹さんがいる
6,本多正信の【死後に起こった出来事】とは?
死後に、【宇都宮釣り天井事件】が起こった
以上となります。
本日は当サイトへお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当サイトへお越しくださいませ。
ありがとうございました。










コメント